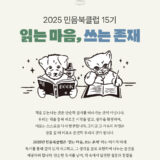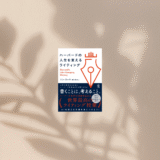2024年の夏~秋にかけて、翻訳者の方々が登壇するイベントにオンラインで参加しました。
1つめは、村井理子さんと井口耕二さんによるイベント。
もう1つは、通訳翻訳ジャーナル主催のイベントで、文芸翻訳家の三辺律子さん、ノンフィクション翻訳家の児島修さん、ダイヤモンド社書籍編集局の畑下裕貴さんなどが登壇されていました。
2つのイベントを聞いてから、翻訳のしかたを変えて数か月。
ようやくやり方も固まってきたので、備忘録として残しておこうと思います。
それまでの翻訳スタイル
スタイルということもありませんが……
それまでは、わからないところがあっても、ひとまず最初から最後まで訳しきる方法で訳していました。
でも、そのやり方だと見直しに時間がかかり、取りこぼしがなかなか減らないことが課題でした。
変更後のスタイル
そんなとき、イベントを拝聴して、自分なりに改善して定着したのが……
・パラグラフ単位で訳し、見なおす(原文と付き合わせてミスはないか、リズムは悪くないか、なめらかに読めるかを都度確認)
・いくつかパラグラフを訳したら小見出し単位で確認、これをくり返す
という方法でした。
それから、今までは別のファイルに用語集とか訳語をまとめていたけれど、これも自分の性格には合いませんでした。
登壇者のみなさんのスタイルからヒントをもらって、訳文の下に羅列するかたちでキーワードをまとめるように変えました。
(検索もすぐにできるし、管理も簡単なので、表記のブレも少なくなった)
こう文字にしてみるとなんてことないのですが、これまではどうしても締め切りを意識しすぎるがあまり気持ちばかり焦っていました。
まずは時間をかけて原文を読み込み、訳文の方向性を決める時間に重きを置いて、じっくりと進めたほうが結局はクオリティも上がる気がしています。
もちろん、要検討な箇所は飛ばすこともありますが、じっくりと訳していくことで各小見出しの要点も把握しやすくなりました。
いまはノンフィクションをおもに訳しているので、これがフィクションになると違ってくるとは思いますが、これまで翻訳の先生方も言っていた「原文を読み、リサーチに時間をかける」ことの大切さがあらためてわかったような気がします。